1. 導入|なぜ今「協賛ブランディング」が注目されるのか?
社会課題への取り組みが企業評価に直結する今、単なる広告やPRでは差別化が難しくなっています。そこで注目されているのが「協賛ブランディング」。CSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・ガバナンス)への関心が高まる中で、共感される企業としての信頼を得る手段として、協賛を通じたブランディングは大きな力を持ちます。
しかし、協賛先を誤れば“お金を払っただけ”で終わり、逆に企業イメージを損なうことも。信頼性のある協賛先を見極め、戦略的に活用することが成果を左右します。
2. 定義|協賛ブランディングとは?
協賛ブランディングとは、社会的意義のある団体・活動・プロジェクトへの協賛を通じて、企業ブランドの信頼性や共感力を高める手法です。
一般的な協賛との違いは以下の通り:
【協賛型】…共感重視。長期的な信頼やブランドイメージの構築を目的とする
【広告型】…露出重視。短期的な集客や知名度向上を目的とする
3. 最近の動向|CSR・ESG重視の潮流と協賛の位置付け
- SDGsやESG投資の広がりにより、中小企業にも社会性ある活動が求められるように
- 補助金・助成金・融資・投資の審査においてCSR実績が評価対象となるケースが増加
- SNS時代の信頼形成には「何をしている会社か」よりも「何に貢献しているか」が重視される
こうした背景から、ただモノやサービスを売るだけでなく、“社会にどう貢献しているか”を伝える手段として協賛は強い説得力を持つようになっています。
4. 実践ポイント|成果につながる協賛ブランディングの手順
ステップ1:協賛先の信頼性をチェック
- 活動の実態はあるか(架空団体に注意)
- 寄付先が明確か(中抜きや不明瞭な団体は避ける)
- 公開実績・掲載事例があるか(ステークホルダーに示せるか)
ステップ2:自社のCSR方針と親和性があるか確認
教育・福祉・環境など、自社理念に合った活動との連携が理想
ステップ3:発信力のある協賛先を選ぶ
- Webサイト・ブログ・SNS・報告書など、多様な発信チャネルがあるか
- 協賛内容を“対外的に見せてくれる”体制があるか
ステップ4:協賛内容を有効活用
- Webサイトや採用ページに掲載
- 補助金申請時の実績として活用
- 顧客や取引先への安心材料として明示
5. よくある失敗と注意点
- 知名度だけで協賛先を選び、効果が出なかった
- CSRの成果を“見せる工夫”がなく、活用できなかった
- 一過性の協賛で終わり、継続性や信頼性に欠けた印象を持たれた
協賛は“名義だけの装飾”にするのではなく、実績として活用し、評価される工夫が不可欠です。
6. 成果が出始める兆候
- 対外資料(パンフレット、提案書)にCSR事例として使えるようになる
- 補助金や助成金の申請書で審査通過率が上がる
- SNS等での発信に反応が出る(いいね・シェア・共感)
- 採用・営業活動で「社会性」が訴求ポイントになる
7. まとめ|信頼される企業へ。協賛の選び方が未来を変える
協賛ブランディングは、単なる「広告宣伝費」ではなく、
- ブランド信頼を高める投資
- 補助金・助成金・投資家評価に活きる資産
- 社会貢献と経営戦略をつなぐ“共感資本”の構築
です。
適切な協賛先を選ぶことで、企業の理念や価値を社会に広め、長期的な成長と信用形成につなげることができます。CSRを戦略的に活用したい企業は、信頼できる協賛先の情報収集から始めてみましょう。
※参考になる協賛事例や具体的な活用例については、別途資料請求やオンライン相談を通じてご確認いただけます。
さらに経営に役立つ情報をお探しの方は
ハイタッチ・マーケティング公式ブログもぜひご覧ください
https://www.hmllp.blog
QRからはこちら
(チャットが開きます)
.png)

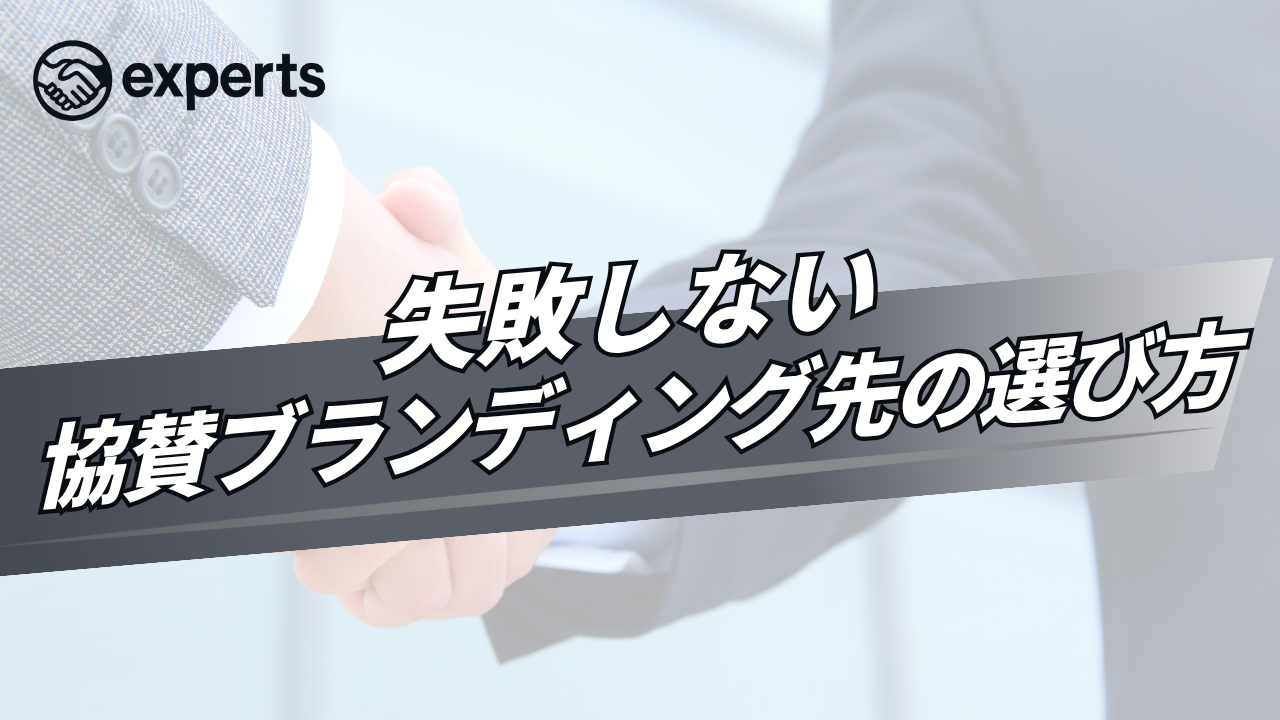
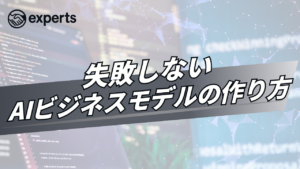
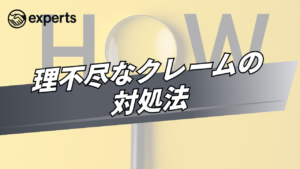




コメント